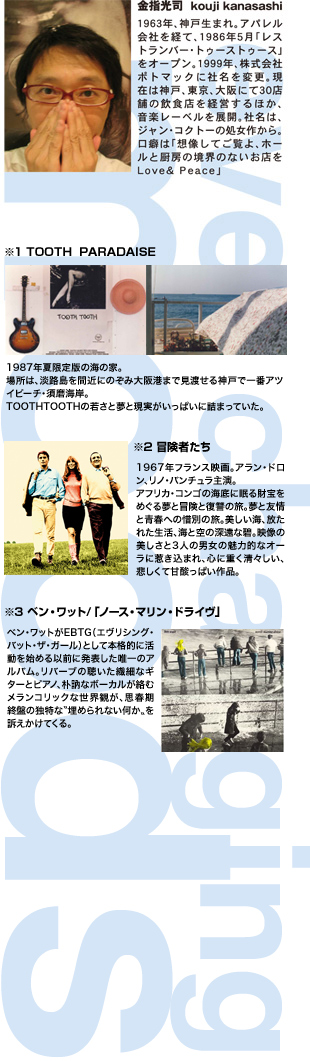
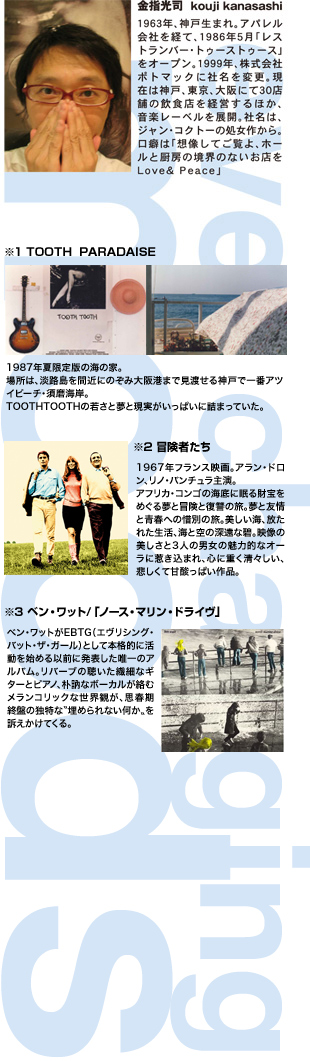
1987年。
会社の沿革から消去された幻の楽園のお話。
昭和62年、「TOOTH TOOTH」誕生の次の年、なんと2号店をいきなり開業することになった。無謀にもほどがあるというものだ。関西の湘南と呼ばれる?須磨ビーチに、たった2ヶ月という期限付きのひと夏だけの伝説を作った。
海の家「TOOTH PARADAISE」(※1)だ。
僕の場合、夏の海イメージはこうだ。
灼熱の太陽の中、色とりどりのパラソルひしめくと浜辺に、寝転がる小麦色の少女たちと日焼け止めのむせかえるような匂い。そんなビーチの猥雑なカラフルな画面と、はしゃぐ子供たちの声が、一瞬ポーズボタンを押されたビデオのように、すべてが静止した真空状態に陥ることがある。海を舞台にした名作アランドロンの「太陽がいっぱい」「冒険者たち」(※2)で感じたものに似ている。それは、甘酸っぱい悲しさと、すがすがしい寂しさに包まれる「太陽の下の孤独」という感覚だ。
ジャクソン・ポロックの絵のような、水着とゴミとを乱雑に敷きつめたビーチを、ベン・ワットの「ノース・マリン・ドライヴ」(※3)を聞きながら眺めたものだ。
そんな僕たちだから、夏の砂浜に似つかわしくない海の家を作ってみたかった。
借金まみれのポケットを裏返し、かき集めたコインでできたバラック小屋。
金づちとのこぎりを手に、自分たちで基礎を作りペンキを塗りトタンを張り巡らせた。
海に向かってヒマワリの一輪ざしを並べた長いカウンターを作った。バンドが演奏できる小さなステージをしつらえ、楽器をかき集めた。帽子とギターを引っかけたベニヤ板の壁には、なぜだか露わになったセクシーな女の足のポスターが貼られていた。
そんなスノッブに構えていた僕たちは、海の神ポセイドンの怒りに触れたのかもしれない。
その夏は冷夏で、2ヶ月の2分の1は雨が降り、台風の当たり年だった。
「ここは無人島か?」と思うくらい暇な日が続いた。
漁師と野良犬しか見かけない。
おかげで、素潜りで魚を突くのが上手になった。
どんより曇った鼠色の空と海のはざまを一日中眺める。
毎日ギターを爪弾いた。
おかげで、「イパネマの娘」を弾けるほど上手になった。
防犯上の問題もありそこに寝泊まりしていたのだが、湿度と暑さでべとべとの体に潮と砂がへばりつき、屋根があるだけましの寝床は、フナ虫と巨大海蚊の攻撃にさらされた。
台風の日は、激しくトタンに叩きつける雨風で、会話できないどころか屋根と鼓膜がすべてめくりあげられるような状態の中、一晩中ずぶぬれになって土砂を積み上げた。
一転、忙しくなると朝から晩まで焼きそばを焼き続けた。焼けつく砂浜の暑さと、鉄板の暑さで意識朦朧となりながら焼き続けた。初めのころは、水着の女の子にどぎまぎしていたのだが、すぐに何もかもが焼きそばに見えるようになった。
みんなに集まってもらうために、イベントやビーチパティーも催した。たくさんのハッピーやスマイル、ラブやピースが生まれたと思う。ギラギラ太陽の下、RockしDanceした。
暑い夏がまたやってきた。
みんなで海へドライヴGO!GO!
いかれたあの子に声かけりゃ
「あんたはまだまだ子供だよ」
どうにもならないこの気持ち。
やるせないのさSUMMER TIME BLUES。
子供バンド(懐かしー!)“SUMMER TIME BLUES”
たくさんの苦い思い出と甘い夢の時間が流れた。
何もかもオレンジ色に溶け出す夕刻、飼い猫の腹毛までが黄金色になびいてた。
月明かりの深夜、浜の浅瀬にビーチベットを持ち出し、純銀のようにぎらつく海を枕にまどろんだ。
“TOOTH PARADAISE”。
奇跡のように美しく、ちょっぴり切ない夏だった。
